中小企業診断士の資格情報
スポンサード リンク
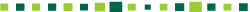
当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

中小企業診断士の資格の事はよく聞くけど、
実際に何をしているかを説明できる人は、
そんなに多くはないかもしれませんね?
簡単に言うと、中小企業に対する
経営コンサルタントの仕事がメインで、
中小企業をさまざまな面から診断し、
経営課題を解決するための
適切なアドバイスをしたりします。
特に日本では中小企業の割合が9割を超えるとも
言われているので、非常にニーズも高い資格です。
そして、中小企業診断士の資格は、
中小企業支援法に基づいて、経済産業大臣が
登録する"経営コンサルタント"としての唯一の国家資格です。
中小企業診断士の主な仕事
中小企業診断士は、大まかに言うと下記のような業務を行っています。
- 経営計画・業務改善などの経営管理・指導業務
- 資金繰りや税務対策などの財務関連の業務
- 開業/資金計画などの企業創業に関する業務
- 販売促進・販路拡大などの営業管理に関する業務
- マーケティング調査・商品開発などの調査・研究開発業務
- 在庫や物流に至る生産・管理業務
- 就業規則作成や社員研修などの人事教育関連の業務
- 研修やセミナーなどの講師・講演活動
- 雑誌への寄稿や書籍の執筆活動

通信講座の無料資料請求はコチラ
中小企業診断士の資格試験情報について
下記が、中小企業診断士の検定試験概要になります。
| 資格名 | 中小企業診断士 |
|---|---|
| 資格の概要 | 中小企業支援法に基づいて、経済産業大臣が登録する"経営コンサルタント"としての唯一の国家資格が、中小企業診断士の資格です。 中小企業診断士の大多数は企業に属して活動している方が多いですが、独立して中小企業をさまざまな面から診断し、経営課題を解決するための適切なアドバイスを行なうコンサルタント業を営んでいる方も多いです。 |
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 受験資格 | 「1次試験」 特になし 「2次試験(筆記試験)」 第1次試験合格者 ※1次試験合格(全科目合格)年度とその翌年度に限り有効 「2次試験(口述試験)」 当該年度の2次筆記試験合格者 ※口述試験を受ける資格は当該年度のみ有効(翌年度への持ち越しは不可) |
| 願書受付・方法等 | ◆第1次試験:5月中旬~5月下旬 ◆第2次試験:8月下旬~9月中旬 |
| 受験区分等 | 中小企業診断士試験 |
| 試験日 | 「1次試験」:8月上旬の土日(2日間) 「2次試験(筆記試験)」:10月下旬(1日間) 「2次試験(口述試験)」:例年1月中旬 |
| 試験科目・ 内容・方法等 |
◆第1次試験(マークシート方式):[筆記試験/2日間で7科目] [1日目] 1.経済学・経済政策 [配点/100点] (1)国民経済計算の基本的概念 (2)主要経済指標の読み方 (3)財政政策と金融政策 (4)国際収支と為替相場 (5)主要経済理論 (6)市場メカニズム (7)市場と組織の経済学 (8)消費者行動と需要曲線 (9)企業行動と供給曲線 (10)産業組織と競争促進 (10)その他経済学・経済政策に関する事項 2.財務・会計 [配点/100点] (1)簿記の基礎 (2)企業会計の基礎 (3)原価計算 (4)経営分析 (5)利益と資金の管理 (6)キャッシュフロー(CF) (7)資金調達と配当政策 (8)投資決定 (9)証券投資論 (10)企業価値 (11)デリバティブとリスク管理 (12)その他財務・会計に関する事項 3.企業経営理論 [配点/100点] (1)経営戦略論 (2)組織論 (3)マーケティング論 4.運営管理(オペレーション・マネジメント) [配点/100点] (1)生産管理 ・生産管理概論 ・生産のプラニング ・生産のオペレーション ・その他生産管理に関する事項 (2)店舗・販売管理 ・店舗/商業集積 ・商品仕入/販売(マーチャンダイジング) ・商品補充/物流 ・流通情報システム ・その他店舗/販売管理に関する事項 [2日目] 5.経営法務 [配点/100点] (1)事業開始、会社設立及び倒産等に関する知識 (2)知的財産権に関する知識 (3)取引関係に関する法務知識 (4)企業活動に関する法律知識 (5)資本市場へのアクセスと手続 (6)その他経営法務に関する事項 6.経営情報システム [配点/100点] (1)情報通信技術に関する基礎的知識 ・情報処理の基礎技術 ・情報処理の形態と関連技術 ・データベースとファイル ・通信ネットワーク ・システム性能 ・その他情報通信技術に関する基礎的知識に関する事項 (2)経営情報管理 ・経営戦略と情報システム ・情報システムの開発 ・情報システムの運用管理 ・情報システムの評価 ・外部情報システム資源の活用 ・情報システムと意思決定 ・その他経営情報管理に関する事項 7.中小企業経営・中小企業政策 [配点/100点] (1)中小企業経営 ・経済/産業における中小企業の役割、位置づけ ・中小企業の経営特性と経営課題 (2)中小企業政策 ・中小企業に関する法規と政策 ・中小企業政策の役割と変遷 (3)その他中小企業経営・中小企業政策に関する事項 ※科目合格制をとっており、合格した科目は3年間有効となり、期間内に第1次試験を再度受験する際は、合格し受験前に申請したた科目のみ免除されます。 ※3年間ですべての科目に合格すれば、第1次試験合格となります。 ◆第2次試験:[1事例ごとに600字~800字の論述式] 1.筆記試験/4事例 ・中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 Ⅰ(組織[人事を含む]) ・中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 Ⅱ(マーケティング・流通) ・中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 Ⅲ(生産・技術) ・中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 Ⅳ(財務・会計) 2.口述試験 中小企業の診断及び助言に関する能力について、筆記試験の事例などをもとに個人面接を行う |
| 試験時間 | ◆第1次試験 [1日目] ・経済学・経済政策:60分 ・財務・会計:60分 ・企業経営理論: ・運営管理(オペレーション・マネジメント):60分 [2日目] ・経営法務:60分 ・経営情報システム:60分 ・中小企業経営・中小企業政策:60分 ◆第2次試験 1.筆記試験/4事例 ・中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 Ⅰ:80分 ・中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 Ⅱ:80分 ・中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 Ⅲ:80分 ・中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 Ⅳ:80分 2.口述試験 1人当たり約10分の面接 |
| 合格基準 | 「1次試験」 ①総点数による合格基準 免除科目を除く全科目を受験し、総点数の60%以上であって、かつ1科目でも満点の40%未満のないことを基準とし、試験委員会が相当と認めた得点比率とする。 ②科目ごとによる合格基準 科目合格基準は、満点の60%を基準として、試験委員会が相当と認めた得点比率とする。 「2次試験(筆記試験・口述試験)」 筆記試験における総点数の60%以上で、かつ1科目でも満点の40%未満がなく、口述試験における評定が60%以上であることを基準とする。 |
| 合格の有効期限 (1次試験) |
①1次試験合格(全科目合格)の有効期間は2年間 ※合格年度とその翌年度まで2次試験を受験できる ②1次試験合格までの科目合格の有効期間は3年間 ※翌年度と翌々年度まで合格した科目を免除申請できる ※3年以内に7科目のすべてに合格することで1次試験合格となります。 |
| 合格の有効期限 | 2次試験合格後、3年以内に実務従事・実務補習を受ける必要がある。 |
| 合格発表 | 「1次試験」9月下旬 「2次試験」1月中旬~下旬 ※2次試験 筆記試験の結果発表:例年1月上旬 |
| 受験料 | 「1次試験」14,500円 「2次試験」17,800円 |
| 実施会場 | 「1次試験」 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇・金沢・四国 「2次試験」 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡 |
| 実施団体等 | 社団法人 中小企業診断協会 |
| 管轄 | 経済産業省 |
![[中小企業診断士] 情報/人気の国家資格取得](./img/header.jpg)

