消防設備士の資格試験情報について
スポンサード リンク
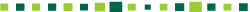
当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
ヒューマンアカデミーの通信講座「たのまな」
⇒無料資料請求はコチラ
| 資格名 | 消防設備士 |
|---|---|
| 資格の概要 | 消防設備士とは、劇場・デパート・ホテルなどの建物に、その用途・規模・容人員に応じて、設置を法律により義務づけられている、消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、救助袋などの避難設備の設置工事、点検整備を行う専門家で、それらを行うために必要な国家資格の事 そして、資格取得のための試験は都道府県知事の委託を受けた財団法人消防試験研究センター(各都道府県支部)が実施し、消防設備士の資格保有を証明するために、都道府県知事から交付される公文書を消防設備士免状といいます。 消防設備士の資格には、甲種と乙種の2種類があり、下記の様にそれぞれ指定区分に応じた、消防用設備等の工事・整備及び点検をすることができます(工事は甲種のみ)。 【乙種】 第1類:屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 第2類:泡消火設備 第3類:不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 第4類:自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 第5類:金属製避難はしご、救助袋、緩降機 第6類:消火器 第7類:漏電火災警報器 【甲種】 特類:特殊消防用設備等 第1類:屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 第2類:泡消火設備 第3類:不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 第4類:自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 第5類:金属製避難はしご、救助袋、緩降機 |
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 受験資格 | 【乙種】 特に制限はなく、誰でも受験可能 【甲種】 [特類]: 甲種特類を受験するには、甲種第1類から第3類までのいずれか一つ、甲種第4類及び甲種第5類の3種類以上の免状の交付を受けていることが必要です。 [特類以外]: ◆学歴による受験資格: ◇学校教育法による大学、短期大学、又は高等専門学校(5年制)において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業された方 ◇学校教育法による高等学校及び中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業された方 *ただし、指定されている学科名の中に、該当するものがない場合は、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を8単位以上修めて卒業されたことを単位修得証明書で確認を受ける必要があります。 ◇旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業された方 *ただし、指定されている学科名の中に、該当するものがない場合は、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修めて卒業されたことを単位修得証明書で確認を受ける必要があります。 ◇外国に所在する学校で、日本における大学、短期大学、高等専門学校又は高等学校に相当するもので、指定した学科と同内容の学科又は課程を修めて卒業された方 ◇学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校(5年制)又は専修学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を、大学にあっては大学設置基準、短期大学にあっては短期大学設置基準、高等専門学校にあっては高等専門学校設置基準及び専修学校においては専修学校設置基準による単位を15単位以上修得された方 ◇学校教育法による各種学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を講義については15時間、実習については30時間、実験、実習及び実技については45時間の授業をもってそれぞれ1単位として15単位以上修得された方 ◇学校教育法による大学、短期大学及び高等専門学校(5年制)の専攻科において、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方 ◇防衛庁設置法による防衛大学校及び防衛医科大学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方 ※その他、細かい規定が色々ありますので、試験実施先HPにてご確認ください! ◆国家資格による受験資格: ◇甲種消防設備士(試験の一部免除有) 受験する類以外の甲種消防設備士免状の交付を受けている者 ◇乙種消防設備士 乙種消防設備士免状の交付を受けた後2年以上、工事整備対象設備等の整備の経験を有する者 ◇技術士(試験の一部免除有) 技術士法第4条第1項による技術士第2次試験に合格された者 (試験の一部免除がされる類は技術士の部門により限定されます) ◇電気工事士(試験の一部免除有) 1.電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士免状の交付を受けている者 2.電気工事士法施行規則による旧電気工事技術者検定合格証明書の所持者で、電気工事士免状の交付を受けているとみなされる者 ◇電気主任技術者(試験の一部免除有) 電気事業法第44条第1項に規定する第1種、第2種又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 ※その他、細かい規定が色々ありますので、試験実施先HPにてご確認ください! |
| 願書受付・方法等 | 全国各地で年1回から数回実施 東京では種ごとに年3〜7回実施 詳細は、地域の消防試験研究センター支部にご確認ください! |
| 受験区分等 | 甲種、乙種 |
| 試験期日 | 全国各地で年1回から数回実施 東京では種ごとに年3〜7回実施 詳細は、地域の消防試験研究センター支部にご確認ください! |
| 試験科目・ 内容・方法等 |
【乙種】 [全類]: ◆筆記試験(4肢択一) ・消防関係法令:10問 ・基礎的知識:5問 ・消防用設備等の構造・機能・整備:15問 ◆実技試験(記述式) ・鑑別等:5問 【甲種】 [特類]:筆記試験 ・消防関係法令:15問 ・工事整備対象設備等の構造・機能・工事・設備:15問 ・工事整備対象設備等の性能に関する火災・防火:15問 [特類以外]: ◆筆記試験(4肢択一式) ・消防関係法令:15問 ・基礎的知識:10問 ・消防用設備等の構造・機能・工事・整備:20問 ◆実技試験(写真・イラスト・図面等による記述) ・鑑別等:5問 ・製図:2問 【一部科目免除制度】 ※下記に該当する者は、申請により試験科目の一部が免除になります(試験時間も短縮になります) ・消防設備士 ・電気工事士 ・電気主任技術者 ・技術士等 ・日本消防検定協会又は指定検定機関の職員で、型式認証の試験の実施業務に2年以上従事した者 ・5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防学校の教育訓練のうち専科教育の機関科を修了した者 ※それぞれ、免除科目が異なりますので、試験実施先HPにてご確認ください! ※また、甲種特類試験には、科目免除はありません。 |
| 試験時間 | 【乙種】 [全類]:1時間45分 【甲種】 [特類]:2時間45分 [特類以外]:3時間15分 |
| 合格基準・合格率 ・レベル等 |
【乙種】: 筆記試験において、各科目毎に40%以上で全体の出題数の60%以上、かつ、実技試験において60%以上の成績を修めた者 (*試験の一部免除がある場合は、免除を受けた以外の問題で上記の成績を修めた方) 【甲種】: 各科目毎に40%以上で全体の出題数の60%以上の成績を修めた方 |
| 合格発表 | 支部別に合格者の受験番号を公示するとともに、受験者には郵便ハガキで合否の結果を直接通知 ※尚、消防設備士免状を有する者は、消防用設備等の工事又は整備に関する新しい知識、技能の習得のため、免状交付後2年以内に、その後は5年以内ごとに、都道府県知事、又は総務大臣が指定する講習機関が行う講習に参加する必要があります。 (実際には、都道府県単位で消防設備関連団体が委託実施) |
| 受験料 | 【乙種】:3,400円(非課税) 【甲種】:5,000円(非課税) その他、下記の様な手数料が発生します。 ◇消防設備士免状交付手数料:2,800円 (同時に複数類の免状を申請する場合は、2,800円×複数類) |
| 試験場所 | 全国各地 |
| 実施団体等 | 財団法人 消防試験研究センター 各都道府県支部 |
| 管轄 | 総務省 |
![[消防設備士] 情報/人気の国家資格取得](./img/header.jpg)
