弁理士試験情報について
スポンサード リンク
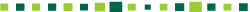
当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
 ケイコとマナブ.net⇒無料資料請求はコチラ
ケイコとマナブ.net⇒無料資料請求はコチラ 資格GETへの近道はスクール探しから【Gooスクール】⇒無料資料請求はコチラ
資格GETへの近道はスクール探しから【Gooスクール】⇒無料資料請求はコチラ| 資格名 | 弁理士試験 |
|---|---|
| 資格の概要 | 弁理士試験は、弁理士になろうとする方が弁理士として必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とした試験で、弁理士試験に合格し、実務修習を修了された方は、「弁理士となる資格」が得られます。 |
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 受験資格 | 学歴、年齢、国籍等による制限は一切なし |
| 願書受付・方法等 | ◆受験願書配布: 3月上旬〜4月上旬 ・インターネット願書請求:2月上旬〜3月下旬 ◆願書受付:4月上旬 |
| 受験区分等 | 弁理士試験 |
| 試験期日 | ◆短答式筆記試験:5月中旬〜下旬 ◆論文式筆記試験 ◇必須科目:6月下旬〜7月上旬 ◇選択科目:7月下旬〜8月上旬 ◆口述試験:10月中旬〜下旬 |
| 試験科目・ 内容・方法等 |
◆短答式筆記試験 [出題形式]:5枝択一:マークシート方式 [出題数]:60問 [試験科目]: ・工業所有権(特許、実用新案、意匠、商標)に関する法令 ・工業所有権に関する条約 ・著作権法 ・不正競争防止法 [出題配分比(おおよその比率)] ・特許/実用新案:2 ・意匠:1 ・商標:1 ・条約:1 ・著作権法/不正競争防止法:1 ◆論文式筆記試験 [試験科目]: ◇必須科目 ・工業所有権に関する法令 1.特許・実用新案に関する法令 2.意匠に関する法令 3.商標に関する法令 ◇選択科目 ※下記の6科目のうち、受験願書提出時にあらかじめ選択する1科目 1.理工I(工学) 基礎材料力学、流体力学、熱力学、制御工学、基礎構造力学、建築構造、土質工学、環境工学 2.理工II(数学・物理) 基礎物理学、計測工学、光学、電子デバイス工学、電磁気学、回路理論、エネルギー工学 3.理工III(化学) 化学一般、有機化学、無機化学、材料工学、薬学、環境化学 4.理工IV(生物) 生物学一般、生物化学、生命工学、資源生物学 5.理工V(情報) 情報理論、情報工学、通信工学、計算機工学 6.法律(弁理士の業務に関する法律) 民法(総則、物権、債権)、民事訴訟法、著作権法、不正競争防止法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、行政法、国際私法 [出題配分比(おおよその比率)] ・特許/実用新案:2 ・意匠:1 ・商標:1 ・著作権法:1 ◆口述試験 [試験方式]:面接方式 [試験科目]: ・工業所有権に関する法令 1.特許・実用新案に関する法令 2.意匠に関する法令 3.商標に関する法 【試験免除制度】 ◆短答式筆記試験の免除: ◇短答式筆記試験合格者 ・短答式筆記試験の合格発表の日から2年間、短答式筆記試験の全ての試験科目が免除 ◇工業所有権に関する科目の単位を修得し大学院を修了した方(ただし、平成20年1月以降に進学した方) ・大学院の課程を修了した日から2年間、工業所有権に関する法令、工業所有権に関する条約の試験科目が免除(事前申請が必要) ◇特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した方 ・工業所有権に関する法令、工業所有権に関する条約の試験科目が免除 ◆論文式筆記試験(必須科目)の免除: ◇論文式筆記試験(必須科目)合格者 ・論文式筆記試験の合格発表の日から2年間、論文式筆記試験(必須科目)が免除 ◇特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した方 ◆論文式筆記試験(選択科目)の免除: ◇論文式筆記試験(選択科目)合格者 ・論文式筆記試験の合格発表の日から永続的に論文式筆記試験(選択科目)が免除 ◇修士又は博士の学位を有する方 ・論文式筆記試験(選択科目)の[科目]に関する研究により学校教育法第104条に規定する修士又は博士の学位を有する方のうち、学位授与に係る論文の審査に合格した方は、論文式筆記試験(選択科目)が免除 ◇専門職の学位を有する方 ・弁理士法施行規則で定める公的資格者(技術士、一級建築士、第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、薬剤師、情報処理技術者、電気通信主任技術者、司法試験合格者、司法書士、行政書士)については、各資格に対応する論文式筆記試験(選択科目)が免除(事前申請が必要) ◆口述試験の免除: ◇特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した方 |
| 試験時間 | ◆短答式筆記試験:3.5時間 ◆論文式筆記試験 ◇必須科目 ・特許/実用新案:2時間 ・意匠:1.5時間 ・商標:1.5時間 ◇選択科目:1.5時間 ◆口述試験 ・工業所有権に関する法令 1.特許・実用新案に関する法令:約10分程 2.意匠に関する法令:約10分程 3.商標に関する法:約10分程 |
| 合格基準・合格率 ・レベル等 |
◆短答式筆記試験: 得点が一定比率(おおむね60%)以上の者のうち、論文式筆記試験を適正に行う視点から許容できる最大限度の受験者数から設定 ◆論文式筆記試験: ※[必須科目]の合格基準を満たし、かつ[選択科目]の合格基準を満たすこと ◇必須科目 得点の合計が、満点に対して54%の得点を基準として工業所有権審議会が相当と認めた得点以上であること。(ただし、47%未満の得点の科目が一つもないこと) ※必須3科目のうち、1科目でも受験しない場合は、必須科目全ての科目の採点を行いません。 ◇選択科目 科目の得点(素点)が満点の60%以上であること ◆口述試験: 採点基準をA、B、Cのゾーン方式とし、合格基準はC評価が2つ以上ないこと |
| 合格発表 | 例年1月中旬頃 |
| 受験料 | 12,000円(特許印紙にて納付) |
| 試験場所 | ◆短答式筆記試験: 東京、大阪、仙台、名古屋、福岡 ◆論文式筆記試験: 東京、大阪 ◆口述試験:東京 |
| 実施団体等 | 経済産業省 特許庁 |
| 管轄 | 経済産業省 |
![[弁理士試験] 情報/人気の国家資格取得](./img/header.jpg)
![インディビジョン[スクール]](./img/button_b1.jpg)
