放射線取扱主任者の資格試験情報について
スポンサード リンク
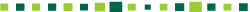
当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
| 資格名 | 放射線取扱主任者 |
|---|---|
| 資格の概要 | 放射線取扱主任者は、単なる放射線管理担当者でなく、放射線障害防止法※1に基づき、監督者として誠実にその職務を遂行する者の事で、放射線取扱主任者免状は文部科学大臣が与える国家資格である。 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づいた放射性同位元素あるいは放射線発生装置の使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者は、同法に基づき、放射線障害の防止について監督を行わせるために放射線取扱主任者を事業所につき1名以上選任し届け出なければならない。 主任者免状には3種類あり、第1種及び第2種は文部科学大臣登録試験機関が主任者試験を行い、第3種は主任者試験が不要。 第1種及び第2種の主任者試験合格者は、文部科学大臣登録資格講習機関の資格講習を受講することによって国家資格を取得でき、第3種は資格講習を受講するだけで国家資格の取得が可能 【主任者の選任区分】 ◆第3種の事業者: ・下限数量の1000倍以下の密封放射性同位元素の届出使用者 ・届出販売業者(取扱が非実物、取扱実物は許可届出使用者) ・届出賃貸業者(取扱が非実物、取扱実物は許可届出使用者) ◆第2種の事業者: ・下限数量の1000倍を超え10テラベクレル未満の密封放射性同位元素の許可使用者 及び、第3種で指定された事業者 ◆第1種の事業者: ・下記の許可使用者 a.非密封放射性同位元素 b.放射線発生装置 c.10テラベクレル以上の密封放射性同位元素 ・許可廃棄業者 及び、第2種・第3種で指定された事業者 ※1[障害防止法の放射線] 1.アルファ線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線 2.中性子線 3.ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴って発生する特性エックス線に限る) 4.1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線 主任者の主な職務は、下記の通りである。 1.放射線障害予防規程の制定及び改廃への参画 2.放射線障害予防上重要な計画作成への参画 3.法令に基づく官辺手続きの審査 4.立入検査等の立会い 5.異常及び事故の原因調査への参画 6.事業者に対する意見の具申 6.使用状況、施設、帳簿及び書類等の審査 7.関係者への助言、勧告及び指示 8.その他放射線障害予防に関し必要な事項 |
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 受験資格 | 特に制限はなし |
| 願書受付・方法等 | 5月下旬~6月下旬 |
| 受験区分等 | 第1種、第2種 |
| 試験期日 | ◆第2種放射線取扱主任者:8月下旬 ◆第1種放射線取扱主任者:8月下旬の2日間 |
| 試験科目・ 内容・方法等 |
[問題形式]:マークシート方式・全科目択一式 ◆第2種放射線取扱主任者 1.放射性同位元素による放射線障害の防止に関する管理技術Ⅰ(放射線の測定に関する技術並びに物理学、化学及び生物学のうち、放射線に関するものを含む):[5問] 2.放射性同位元素による放射線障害の防止に関する管理技術Ⅱ(放射線の測定に関する技術並びに物理学、化学及び生物学のうち、放射線に関するものを含む):[30問] 3.放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律に関する課目:[30問] ◆第1種放射線取扱主任者 [一日目] 1.物理学、化学及び生物学のうち放射線に関するもの:[6問] 2.物理学のうち放射線に関するもの:[30問] 3.化学のうち放射線に関するもの:[30問] [二日目] 4.放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する管理技術並びに放射線の測定に関する技術:[6問] 5.生物学のうち放射線に関するもの:[30問] 6.放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する法令:[30問] |
| 試験時間 | ◆第2種放射線取扱主任者 1.放射性同位元素による放射線障害の防止に関する管理技術Ⅰ(放射線の測定に関する技術並びに物理学、化学及び生物学のうち、放射線に関するものを含む):105分 2.放射性同位元素による放射線障害の防止に関する管理技術Ⅱ(放射線の測定に関する技術並びに物理学、化学及び生物学のうち、放射線に関するものを含む):75分 3.放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律に関する課目:75分 ◆第1種放射線取扱主任者 [一日目] 1.物理学、化学及び生物学のうち放射線に関するもの:105分 2.物理学のうち放射線に関するもの:75分 3.化学のうち放射線に関するもの:75分 [二日目] 4.放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する管理技術並びに放射線の測定に関する技術:105分 5.生物学のうち放射線に関するもの:75分 6.放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する法令:75分 |
| 合格基準・合格率 ・レベル等 |
試験課目ごとの得点が5割以上であり、かつ、全試験課目の合計得点が6割以上であること ◆第2種放射線取扱主任者:合格率は30~35%前後 ◆第1種放射線取扱主任者:合格率は20~25%前後 合格率は年度によりばらつきがあるが、難易度は高い |
| 合格発表 | 10月下旬 ※主任者試験に合格しただけでは主任者に選任できない。 第1種・第2種主任者試験合格後、資格講習機関による資格講習を受講し修了試験に合格すれば、本人の申請により文部科学大臣の免状交付が可能になる。 ※文部科学大臣登録資格講習機関による資格講習は、下記の通りである 【第3種】(講習のみで資格取得が可能) ◇財団法人電子科学研究所: [講習料] 90,000円(税込) [最大人員] 18人 [講習期間] 2日 [講習場所] 大阪 ◇原子力研究開発機構: [講習料] 94,500円(税込) [最大人員] 32人 [講習期間] 2日 [講習場所] 茨城 ◇社団法人日本アイソトープ協会: [講習料] 94,500円(税込) [最大人員] 32人 [講習期間] 2日 [講習場所] 東京 ◇財団法人原子力安全技術センター: [講習料] 110,600円(税込) [最大人員] 36人 [講習期間] 2日 [講習場所] 青森、東京、大阪、名古屋、福岡 【第2種】 ◇財団法人電子科学研究所: [講習料] 100,000円(税込) [最大人員] 18人 [講習期間] 3日 [講習場所] 大阪 ◇財団法人原子力安全技術センター: [講習料] 112,500円(税込) [最大人員] 32人 [講習期間] 3日 [講習場所] 東京、大阪、京都 【第1種】 ◇原子力研究開発機構: [講習料] 170,205円(税込) [最大人員] 32人 [講習期間] 5日 [講習場所] 茨城 ◇社団法人日本アイソトープ協会: [講習料] 170,205円(税込) [最大人員] 32人 [講習期間] 5日 [講習場所] 東京 【定期講習】 文部科学大臣登録定期講習機関が主任者の資質向上を図るために定期的に実施する講習で、事業者は放射線障害防止法に基づき、主任者に受講期限までに定期講習を受講させる必要がある。 ◆許可届出使用者・許可廃棄業者 主任者選任後1年以内、以後は受講後3年以内 (主任者選任前1年以内に受講の者は受講後3年以内) ◆届出販売業者・届出賃貸業者 主任者選任後1年以内、以後は受講後5年以内 (主任者選任前1年以内に受講の者は受講後5年以内) |
| 受験料 | ◆第2種放射線取扱主任者:9,900円(税込) ◆第1種放射線取扱主任者:13,900円(税込) |
| 試験場所 | 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、福岡市 |
| 実施団体等 | 財団法人 原子力安全技術センター |
| 管轄 | 文部科学省 科学技術・学術政策局 原子力安全課 放射線規制室 |
![[放射線取扱主任者] 情報/人気の国家資格取得](./img/header.jpg)





