臭気判定士の資格試験情報について
スポンサード リンク
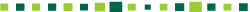
当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
| 資格名 | 臭気判定士 |
|---|---|
| 資格の概要 | 臭気判定士とは、分析機器による測定法ではなく、人の嗅覚を用いる嗅覚測定法を行うための資格であり、パネルの選定・試料の採取・試験の実施・結果の求め方まで全てを管理・統括する責任者で、臭気の濃さの正しい測定、評価により環境保全に貢献する臭気環境分野で初めての国家資格です。 資格取得には、社団法人におい・かおり環境協会が実施する臭気判定士試験(筆記)と、各検査機関で実施する嗅覚検査に合格する必要がある。 |
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 受験資格 | 18歳以上(学歴、実務経験を問わず) |
| 願書受付・方法等 | 7月上旬〜9月上旬 |
| 受験区分等 | 臭気判定士 |
| 試験期日 | 11月中旬 【嗅覚検査】 全国各地の嗅覚検査機関で随時実施 筆記試験合格前でも後でも受験可能で、検査合格後1年間有効 |
| 試験科目・ 内容・方法等 |
【筆記試験:出題内容】 [出題形式]:マークシート方式(五肢択一又は数値解答) 1.嗅覚概論:10問(各1点) ・ヒトの嗅覚の仕組みやにおいの役割などに関する事項 ・嗅覚の順応や閾値など、嗅覚の基本的な特性に関する事項 ・嗅覚とにおい物質の関係に関する事項 ・嗅覚検査やパネルの選定と管理に関する事項 ・においの評価に関する事項 2.悪臭防止行政:10問(各1点) ・規制地域及び規制基準に関する事項 ・悪臭原因物及び悪臭苦情に関する事項 ・臭気判定士(臭気測定業務従事者)に関する事項 ・その他、悪臭防止法、施行令、施行規則、告示等の内容に関する基本的事項 ・臭気発生源及び悪臭防止対策に関する事項 3.悪臭測定概論:10問(各1点) ・嗅覚測定法の基本的な考え方に関する事項 ・特定悪臭物質の特性及び測定に係る基礎的な知識に関する事項 ・嗅覚測定の精度管理・安全管理に関する事項 ・臭気調査、排ガス流量の測定、臭気の拡散等に関する基礎的な事項 ・臭気排出強度、脱臭効率の計算など測定結果の解析に関する事項 4.分析統計概論:10問(各1点) ・統計の基本的な考え方に関する事項 ・度数分布、代表値、散布度、単回帰、相関等のデータの基本構造に関する事項 ・統計的推定、統計的仮説検定等に関する事項 ・2点試験法、3点試験法等、臭気測定データの統計的処理に関する事項 ・精度管理に用いる用語等に関する事項 5.臭気指数等の測定実務:10問(各1点) ・試料採取に用いる器材とその取り扱いに関する事項 ・試料採取方法に関する事項 ・判定試験に用いる器材とその取り扱いに関する事項 ・判定試験方法に関する事項 5-a.臭気指数の算出(計算問題):5問(各2点) |
| 試験時間 | 13時40分〜16時30分 |
| 合格基準・合格率 ・レベル等 |
参考例:平成22年度の合否判定基準(年度により異なる) (1)総合得点率70%以上 (2)各科目別最低得点率 35%以上 ただし、[臭気指数等の測定実務]については、問41〜50の10題(五肢択一)は35%以上、問51〜55の5題(数値回答)は50%以上 ◆合格率は年度によってかなりまちまちだが、35〜45%前後 |
| 合格発表 | 12月中旬 |
| 受験料 | ◆臭気判定士試験:18,000円(非課税) ◆嗅覚検査:9,000円(非課税) ◆免状申請:3,500円 ◆免状更新・再交付手数料:3,000円 ※免状は有効期間が5年となっているので、更新をする際には改めて嗅覚検査を受ける必要があります。 |
| 試験場所 | 東京・大阪・名古屋 |
| 実施団体等 | 社団法人におい・かおり環境協会 全国各地の嗅覚検査機関 |
| 管轄 | 環境省 |
![[臭気判定士] 情報/人気の国家資格取得](./img/header.jpg)









