公認会計士試験情報について
スポンサード リンク
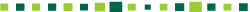
当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
 公認会計士の資格取得を目指すなら簿記・会計資格ナビ
公認会計士の資格取得を目指すなら簿記・会計資格ナビ⇒無料資料請求はコチラ
| 資格名 | 公認会計士試験 |
|---|---|
| 資格の概要 | 公認会計士試験とは、公認会計士になろうとする者に、必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とする国家試験 |
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 受験資格 | 年齢・性別・学歴等に関係なく、誰でも受験可能 |
| 願書受付・方法等 | ◆第I回短答式試験:9月上旬~ 9月中旬 ◆第II回短答式試験:2月中旬~ 2月下旬 |
| 受験区分等 | 公認会計士試験 |
| 試験期日 | ◆第I回短答式試験:12月中旬 ◆第II回短答式試験:5月下旬 ◆論文式試験:8月下旬 |
| 試験科目・ 内容・方法等 |
◆短答式試験 ・財務会計論:40問以内/200点 簿記、財務諸表論、企業等の外部の利害関係者の経済的意思決定に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論 ・管理会計論:20問以内/100点 原価計算、企業等の内部の経営者の意思決定及び業績管理に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論 ・企業法:20問以内/100点 会社法、商法(海商並びに手形及び小切手に関する部分を除く)、金融商品取引法(企業内容等の開示に関する部分に限る)、監査を受けるべきこととされる組合その他の組織に関する法 ・監査論:20問以内/100点 金融商品取引法及び会社法に基づく監査制度及び監査諸基準その他の監査理論 ※短答式試験に合格した者は、申請することによって、合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式試験の免除を受けることが可能 【短答式試験の全部免除該当者】 ・大学等において3年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 ・大学等において3年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 ・高等試験本試験合格者 ・司法試験合格者及び旧司法試験第2次試験合格者 【短答式試験の一部科目免除該当者】 ・税理士となる資格を有する者、又は税理士試験の試験科目のうち簿記論及び財務諸表論の2科目について基準(満点の60%)以上の成績を得た者(基準以上の成績を得たものとみなされる者を含む) ◇免除科目:[財務会計論] ・会計専門職大学院において、 (ⅰ)簿記、財務諸表その他の財務会計に属する科目に関する研究 (ⅱ)原価計算その他の管理会計に属する科目に関する研究 (ⅲ)監査論その他の監査に属する科目に関する研究 により、上記(ⅰ)に規定する科目を10単位以上、(ⅱ)及び(ⅲ)に規定する科目をそれぞれ6単位以上履修し、かつ、上記(ⅰ)から(ⅲ)の各号に規定する科目を合計で28単位以上履修した上で修士(専門職)の学位を授与された者 ◇免除科目:[財務会計論] [管理会計論] 及び [監査論] ・金融商品取引法に規定する上場会社等、会社法に規定する大会社、国、地方公共団体その他の内閣府令で定める法人において会計又は監査に関する事務又は業務に従事した期間が通算して7年以上である者 ◇免除科目:[財務会計論] ◆論文式試験 ・会計学:大問5問/300点 [財務会計論] 簿記、財務諸表論、企業等の外部の利害関係者の経済的意思決定に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論 [管理会計論] 原価計算、企業等の内部の経営者の意思決定及び業績管理に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論 ・監査論:大問2問/100点 金融商品取引法及び会社法に基づく監査制度及び監査諸基準その他の監査理論 ・企業法:大問2問/100点 会社法、商法(海商並びに手形及び小切手に関する部分を除く)、金融商品取引法(企業内容等の開示に関する部分に限る)、監査を受けるべきこととされる組合その他の組織に関する法 ・租税法:大問2問/100点 法人税法、所得税法、租税法総論及び消費税法、相続税法その他の租税法各論 ・選択科目(下記の4科目から選択):大問2問/100点 [経営学] 経営管理及び財務管理の基礎的理論 [経済学] ミクロ経済学、マクロ経済学その他の経済理論 [民法] 民法典第1編から第3編を主とし、第4編及び第5編並びに関連する特別法を含む [統計学] 記述統計及び推測統計の理論並びに金融工学の基礎的理論 【論文式試験の一部科目免除該当者】 ・大学等において3年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 ◇免除科目:[会計学 及び 経営学] ・大学等において3年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 ◇免除科目:[企業法 及び 民法] ・高等試験本試験合格者 ◇免除科目:[上記試験を商法で受験した場合:企業法] ・司法試験合格者 ◇免除科目:[会計学 及び 経営学] ・旧司法試験第2次試験合格者 ◇免除科目:[上記試験を商法又は会計学で受験した場合:企業法又は会計学] ・大学等において3年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 ◇免除科目:[経済学] ・不動産鑑定士試験合格者及び旧鑑定評価法の規定による不動産鑑定士試験第2次試験合格者 ◇免除科目:[経済学又は民法] ・税理士となる資格を有する者 ◇免除科目:[租税法] ・企業会計の基準の設定、原価計算の統一その他の企業会計制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で会計学に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査審査会が認定した者 ◇免除科目:[会計学] ・監査基準の設定その他の監査制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で監査論に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査審査会が認定した者 ◇免除科目:[監査論] ・旧公認会計士試験第2次試験論文式試験において、免除を受けた科目がある者 ◇免除科目: [免除を受けた科目が会計学:会計学] [免除を受けた科目が商法:企業法] [免除を受けた科目が経営学:経営学] [免除を受けた科目が経済学:経済学] [免除を受けた科目が民法:民法] |
| 試験時間 | ◆短答式試験 ・財務会計論:120分 ・企業法:60分 ・管理会計論:60分 ・監査論:60分 ◆論文式試験 ・会計学:300分 [財務会計論] [管理会計論] ・監査論:120分 ・租税法:120分 ・企業法:120分 ・選択科目:120分 [経営学] [経済学] [民法] [統計学] |
| 合格基準・合格率 ・レベル等 |
◆短答式試験 総点数の70%を基準として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率とする。 ただし、1科目につき、その満点の40%に満たないもののある者は、不合格とすることができる。 ◆論文式試験 52%の得点比率を基準として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率とする。 ただし、1科目につき、その得点比率が40%に満たないもののある者は、不合格とすることができる。 論文式試験の採点格差の調整は、標準偏差により行う。 ※論文式試験の一部科目免除資格取得基準 試験科目のうちの一部の科目について、同一の回の公認会計士試験における公認会計士試験論文式試験合格者の平均得点比率を基準として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率以上を得た者を一部科目免除資格取得者とします。 当該科目については、合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式試験において、申請により免除を受けることができます。 |
| 合格発表 | ◆第I回短答式試験:1月中旬 ◆第II回短答式試験:6月下旬 ◆論文式試験:11月中旬 |
| 受験料 | 19,500円の収入印紙を貼り付け納付 |
| 試験場所 | 北海道、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、熊本県、福岡県、沖縄県 |
| 実施団体等 | 公認会計士・監査審査会 |
| 管轄 | 金融庁 |
![[公認会計士試験] 情報/人気の国家資格取得](./img/header.jpg)

