エネルギー管理士の資格試験情報について
スポンサード リンク
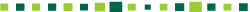
当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
| 資格名 | エネルギー管理士 |
|---|---|
| 資格の概要 | 第1種エネルギー管理指定工場に指定されている規定量以上(熱[燃料等]電気を合算した年間使用量が原油換算3000kl以上)のエネルギーを使用する工場のうち、製造業・鉱業・電気供給業、ガス供給業・熱供給業の5業種では、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、エネルギー消費量に応じ一定人数(1~4名)のエネルギー管理者を選任する必要があります。 エネルギー管理者は、工場におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視、その他経済産業省令で定める業務を管理するのが主な職務です。 エネルギー管理士には、財団法人省エネルギーセンターが実施する「エネルギー管理士試験」に合格するか、「エネルギー管理士講習」を修了し、経済産業大臣に申請する事によって免状が交付されます。 【試験】 ・財団法人省エネルギーセンターが行うエネルギー管理士試験に合格した後、燃料等(電気)の使用の合理化に関する実務に1年以上従事したこと(受験の前後は問わない)をもって、経済産業大臣に免状申請を行うことにより認定され、免状交付が受けられる。 【研修】 ・燃料等(電気)の使用の合理化に関する実務に研修申込時までに3年以上従事していることをもって、エネルギー管理研修を受講し修了試験に合格した後、経済産業大臣に免状申請を行うことにより認定され、免状交付が受けられる。 |
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 受験資格 | 【試験】 学歴、年齢、性別、経験などの制限はありません 【研修】 研修申込時までに、燃料等(電気)の使用の合理化に関する実務経験が3年以上ある者 |
| 願書受付・方法等 | 【試験】 7月上旬~下旬 【研修】 仮申込期間:10月上旬~下旬 研修受講資格審査:11月上旬(実務経験などの資格審査の実施) |
| 受験区分等 | エネルギー管理士 |
| 試験期日 | 【試験】 9月下旬 【研修】 12月中旬(7日間) |
| 試験科目・ 内容・方法等 |
【試験】 [試験形式]:筆記試験(マークシート方式) ◆熱分野専門区分 ◇エネルギー総合管理及び法規(必須基礎科目) ・エネルギーの使用の合理化に関する法律及び命令:1問 ・エネルギー総合管理:2問 ◇燃料と燃焼 ・燃料及び燃焼管理:2問 ・燃焼計算:1問 ◇熱利用設備及びその管理 ・計測及び制御:2問 ・熱利用設備:4問から2問選択 ◇熱と流体の流れの基礎 ・熱力学の基礎:2問 ・流体工学の基礎:1問 ・伝熱工学の基礎:1問 ◆電気分野専門区分 ◇エネルギー総合管理及び法規(必須基礎科目) ・エネルギーの使用の合理化に関する法律及び命令:1問 ・エネルギー総合管理:2問 ◇電気の基礎 ・電気及び電子理論:1問 ・自動制御及び情報処理:1問 ・電気計測:1問 ◇電気設備及び機器 ・工場配電:2問 ・電気機器:2問 ◇電力応用 ・電動力応用:下記4問から2問選択 電気加熱、電気化学、照明、空気調和 [課目合格制度] ※課目別の得点が合格基準に達した課目は「課目合格」となり、4課目合格すればエネルギー管理士試験合格(全課目合格)となります。 課目合格の場合、その試験が行われた年の初めから3年以内に受験する場合、その課目の試験が免除になります。 ただし、課目合格した年の初めから3年を過ぎると、その課目の合格は無効となり、新たに受験することが必要になります。 なお、合格している課目の試験免除期間中(3年間)は、合格している課目について受験することができません。 【研修】 ※選択により熱分野専門区分か電気分野専門区分を選択 ◆必須基礎区分 (Ⅰ)エネルギー総合管理及び法規 ◆熱分野専門区分 (Ⅱ)熱と流体の流れの基礎 (Ⅲ)燃料と燃焼 (Ⅳ)熱利用設備及びその管理 ◆電気分野専門区分 (Ⅱ)電気の基礎 (Ⅲ)電気設備及び機器 ◇工場配電 ◇電気機器 (Ⅳ)電力応用 ◇電動力応用 ◇電気加熱 ◇電気化学 ◇照明 ◇空気調和 ◆修了試験 [課目合格制度] ※前年度に修了試験を受け、修了試験課目の一部について合格し、引き続き次年度の研修を受けようとする方は、前年度に合格した課目の講義及び修了試験が免除されます。 (課目免除期間は課目合格した年の翌年まで) 前年度に不合格であった課目の講義を受け、その課目の修了試験に合格した方は、研修修了者となります。 [受講科目の免除] 第1種電気主任技術者免状又は第2種電気主任技術者免状の交付を受けている方に限り、講義の一部が免除されます。 (ただし、修了試験はすべて受験する必要があります。) |
| 試験時間 | 【試験】 ◆熱分野専門区分 ◇エネルギー総合管理及び法規(必須基礎科目):80分 ◇燃料と燃焼:80分 ◇熱利用設備及びその管理:110分 ◇熱と流体の流れの基礎:110分 ◆電気分野専門区分 ◇エネルギー総合管理及び法規(必須基礎科目):80分 ◇電気の基礎:80分 ◇電気設備及び機器:110分 ◇電力応用:110分 【研修】 ※下記の1時限は40分単位 ◆必須基礎区分 (Ⅰ)エネルギー総合管理及び法規 1.エネルギー総合管理:7時限 2.エネルギーの使用の合理化に関する法律及び命令:2時限 ◆熱分野専門区分 (Ⅱ)熱と流体の流れの基礎 1.熱力学の基礎:8時限 2.流体工学の基礎:4時限 3.伝熱工学の基礎:4時限 (Ⅲ)燃料と燃焼 1.燃料及び燃焼管理:4時限 2.燃焼計算:3時間 (Ⅳ)熱利用設備及びその管理 1.計測及び制御:5時限 2.ボイラ、蒸気輸送・貯蔵装置、蒸気原動機・内燃機関・ガスタービン:4時限 3.熱交換器・熱回収装置、冷凍・空気調和設備:3時限 4.工業炉、熱設備材料:3時間 5.蒸留・蒸発・濃縮装置、乾燥装置、乾留・ガス化装置:3時限 ◆電気分野専門区分 (Ⅱ)電気の基礎 1.電気及び電子理論※:2時限 2.自動制御及び情報処理※:2時限 3.電気計測※:2時限 (Ⅲ)電気設備及び機器 ◇工場配電 1.工場配電の計画※:2時限 2.工場配電の運用※:2時限 3.工場配電の省エネルギー:2時限 ◇電気機器 1.電気機器一般※:2時限 2.回転機と静止器※:2時限 3.電気機器の省エネルギー:2時限 (Ⅳ)電力応用 ◇電動力応用 1.電動力応用一般※:2時限 2.電動力応用の設備:3時限 3.電動力応用の省エネルギー:2時限 ◇電気加熱 1.電気加熱理論及び設備※:2時限 2.電気加熱の省エネルギー:2時限 ◇電気化学 1.電気化学理論及び設備※:2時限 2.電気化学の省エネルギー:2時限 ◇照明 1.照明理論及び設備※:2時限 2.照明の省エネルギー:2時限 ◇空気調和 1.空気調和理論及び設備:2時限 2.空気調和の省エネルギー:2時限 (備考)各講義課目は必須ですが、電気分野専門区分を選択する者のうち第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者に限り、※印の講義課目の受講は免除されます。(修了試験は必須) |
| 合格基準・合格率 ・レベル等 |
【試験】 合格基準は、各課目60%が目安 【研修】 講習実施先にご確認ください! |
| 合格発表 | 【試験】 11月中旬 【研修】 2月上旬頃 |
| 受験料 | 【試験】 17,000円(非課税) 【研修】 新規受講者:70,000円(非課税/テキスト代を含む) 課目合格者:50,000円(非課税/テキスト代を含む) |
| 試験場所 | 【試験地】 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、富山市、大阪府、広島市、高松市、福岡市、那覇市の10ヶ所 【研修地】 仙台市、東京都、名古屋市、大阪府、広島市、福岡市 |
| 実施団体等 | 財団法人 省エネルギーセンター |
| 管轄 | 経済産業省 |
![[エネルギー管理士] 情報/人気の国家資格取得](./img/header.jpg)









