国家公務員総合職の試験情報について
スポンサード リンク
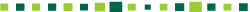
当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
 ヒューマンアカデミーの通信講座「たのまな」
ヒューマンアカデミーの通信講座「たのまな」⇒無料資料請求はコチラ

スクール・通信講座の無料請求はコチラ
| 資格名 | 国家公務員総合職 |
|---|---|
| 資格の概要 | ※平成24年度から国家公務員採用試験が変わります。 国家公務員Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ種試験及び国税専門官などのその他の試験を廃止、総合職試験・一般職試験・専門職試験・経験者採用試験に再編し、総合職試験については、院卒者試験を創設するとともに、院卒者試験に新司法試験合格者を対象にした「法務区分」を、大卒者試験に企画立案に係る基礎的な能力の検証を重視した「教養区分」を設けています。 |
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 受験資格 | ◇院卒者試験[法務区分以外の区分] 受験年度の4月1日における年齢が、30歳未満の者で次に掲げるもの 1.大学院修士課程又は専門職大学院専門職学位課程を修了した者、及び試験の実施年度の3月までに大学院修士課程又は専門職大学院専門職学位課程を修了する見込みの者 2. 人事院が1.に掲げる者と同等の資格があると認める者 ※「同等の資格があると認める者」は、大学院に相当する教育機関の修了者及び修了見込みの者、医学等の6年制学部の卒業者及 び卒業見込みの者 ◇院卒者試験[法務区分] 受験年度の4月1日における年齢が、30歳未満の者で次に掲げるもの 1.法科大学院の課程を修了した者であって司法試験に合格した者 2. 人事院が1.に掲げる者と同等の資格があると認める者 ※「同等の資格があると認める者」は、司法試験予備試験に合格した者であって司法試験に合格した者、又当分の間、旧司法試験合格者にも受験資格を与えることとする。 ◇大卒程度試験 1.受験年度の4月1日における年齢が、21歳以上30歳未満の者 2.受験年度の4月1日における年齢が、21歳未満の者で次に掲げるもの a)大学を卒業した者及び試験の実施年度の3月までに大学を卒業する見込みの者 b)人事院がa)に掲げる者と同等の資格があると認める者 c.[教養区分]にあっては、a)及びb)に掲げるものの他、受験年度の4月1日における年齢が20歳の者 ※採用候補者名簿 最終合格者は、試験の区分ごとに作成する採用候補者名簿(院卒者試験・大卒程度試験ともに3年間有効)に記載され、各府省等では採用候補者名簿に記載された者の中から、面接などを行って採用者を決定 大学卒業後に採用が行われることを前提として、官庁訪問等の採用活動は学部4年次以降に実施(教養区分も同様) |
| 願書受付・方法等 | ◇院卒者試験:4月上旬の1週間程度 ◇院卒者試験[法務区分]:9月中旬の1週間程度 ◇大卒程度試験:4月上旬の1週間程度 ◇大卒程度試験[教養区分]:8月中旬の1週間程度 |
| 受験区分等 | 【院卒者試験】 行政、人間科学、工学、数理科学・物理・地球科学、化学・生物・薬学、農業科学・水産、農業農村工学、森林・自然環境、法務の9区分 【大卒程度試験】 政治・国際、法律、経済、人間科学、工学、数理科学・物理・地球科学、化学・生物・薬学、農業科学・水産、農業農村工学、森林・自然環境、教養の11区分 |
| 試験期日 | 【院卒者試験】 ◆第1次試験:4月下旬 ◆第2次試験・筆記試験:5月下旬 ◆第2次試験・人物試験:5月下旬~6月中旬 【院卒者試験[法務区分]】 ◆第1次試験:9月下旬 ◆第2次試験:10月中旬の2日ほど 【大卒程度試験】 ◆第1次試験:4月下旬 ◆第2次試験・筆記試験:5月下旬 ◆第2次試験・人物試験:5月下旬~6月中旬 【大卒程度試験[教養区分]】 ◆第1次試験:9月下旬 ◆第2次試験:11月上旬~中旬の2週間ほど |
| 試験科目・ 内容・方法等 |
【院卒者試験】 ◆第1次試験・基礎能力試験(多肢選択式):[解答数30題] 公務員として必要な基礎的な能力(知能及び知識)についての筆記試験 ・知能分野[24題] 文章理解 8題、判断・数的推理(資料解釈を含む)16題 ・知識分野[6題] 自然・人文・社会 6題(時事を含む) ◆第1次試験・専門試験(多肢選択式):[解答数40題] 各試験の区分に応じて必要な専門的知識などについての筆記試験 ◆第2次試験・専門試験(記述式) 各試験の区分に応じて必要な専門的知識などについての筆記試験 ・行政区分:[解答数3題] ・その他の区分:[解答数2題] ◆第2次試験・政策課題討議試験 課題に対するグループ討議によるプレゼンテーション能力やコミュニケーション力などについての試験(課題に関する資料の中に英文によるものを含む) ・6人1組のグループを基本として実施 レジュメ作成(25分)→個別発表(1人当たり3分)→グループ討議(30分)→討議を踏まえて考えたことを個別発表(1人当たり2分) ◆第2次試験・人物試験 人柄、対人能力などについての個別面接(参考として性格検査を実施) 【院卒者試験[法務区分]】 ◆第1次試験・基礎能力試験(多肢選択式):[解答数30題] 公務員として必要な基礎的な能力(知能及び知識)についての筆記試験 ・知能分野[24題] 文章理解 8題、判断・数的推理(資料解釈を含む)16題 ・知識分野[6題] 自然・人文・社会 6題(時事を含む) ◆第2次試験・政策課題討議試験 課題に対するグループ討議によるプレゼンテーション能力やコミュニケーション力などについての試験(課題に関する資料の中に英文によるものを含む) ・6人1組のグループを基本として実施 レジュメ作成(25分)→個別発表(1人当たり3分)→グループ討議(30分)→討議を踏まえて考えたことを個別発表(1人当たり2分) ◆第2次試験・人物試験 人柄、対人能力などについての個別面接(参考として性格検査を実施) 【大卒程度試験】 ◆第1次試験・基礎能力試験(多肢選択式):[解答数40題] 公務員として必要な基礎的な能力(知能及び知識)についての筆記試験 ・知能分野[27題] 文章理解 11題、判断・数的推理(資料解釈を含む)16題 ・知識分野[13題] 自然・人文・社会 13題(時事を含む) ◆第1次試験・専門試験(多肢選択式):[解答数40題] 各試験の区分に応じて必要な専門的知識などについての筆記試験 ◆第2次試験・専門試験(記述式) 各試験の区分に応じて必要な専門的知識などについての筆記試験 ◇政治・国際、法律、経済区分:[解答数3題] ◇その他の区分:[解答数2題] ◆第2次試験・政策論文試験:[解答数1題] 政策の企画立案に必要な能力その他総合的な判断力及び思考力についての筆記試験(資料の中に英文によるものを含む) ◆第2次試験・人物試験 人柄、対人能力などについての個別面接(参考として性格検査を実施) 【大卒程度試験[教養区分]】 ◆第1次試験・基礎能力試験(多肢選択式):[解答数40題] 公務員として必要な基礎的な能力(知能及び知識)についての筆記試験 ・Ⅰ部:知能分野[24題] 文章理解 8題、判断・数的推理(資料解釈を含む)16題 ・Ⅱ部:知識分野[30題] 自然10題・人文10題・社会10題(時事を含む) ◆第1次試験・総合論文試験:[解答数2題] 幅広い教養や専門的知識を土台とした総合的な判断力、思考力についての筆記試験 Ⅰ.政策の企画立案の基礎となる教養・哲学的な考え方に関するもの[1題] Ⅱ.具体的な政策課題に関するもの[1題] ◆第2次試験・政策課題討議試験 課題に対するグループ討議によるプレゼンテーション能力やコミュニケーション力などについての試験(課題に関する資料の中に英文によるものを含む) ・6人1組のグループを基本として実施 レジュメ作成(20分)→個別発表(1人当たり3分)→グループ討議(45分)→討議を踏まえて考えたことを個別発表(1人当たり2分) ◆第2次試験・企画提案試験(小論文及び口述式) 企画力、建設的な思考力及び説明力などについての試験 ・Ⅰ部:小論文 (課題と資料を与え、解決策を提案させる) ・Ⅱ部:プレゼンテーション及び質疑応答 (小論文の内容について試験官に説明、その後質疑応答を受ける) ◆第2次試験・人物試験 人柄、対人能力などについての個別面接 ※面接参考資料を事前提出、参考として性格検査を実施 |
| 試験時間 | 【院卒者試験】 ◆第1次試験・基礎能力試験(多肢選択式):2時間20分 ◆第1次試験・専門試験(多肢選択式):3時間30分 ◆第2次試験・専門試験(記述式) [行政区分]:4時間 [その他の区分]:3時間30分 ◆第2次試験・政策課題討議試験(記述式):概ね1時間30分程度 ◆第2次試験・人物試験- 【院卒者試験[法務]】 ◆第1次試験・基礎能力試験(多肢選択式):2時間20分 ◆第2次試験・政策課題討議試験(記述式):概ね1時間30分程度 ◆第2次試験・人物試験- 【大卒程度試験】 ◆第1次試験・基礎能力試験(多肢選択式):3時間 ◆第1次試験・専門試験(多肢選択式):3時間30分 ◆第2次試験・専門試験(記述式) [政治・国際、法律、経済区分]:4時間 [その他の区分]:3時間30分 ◆第2次試験・政策論文試験:2時間 ◆第2次試験・人物試験- 【大卒程度試験】 ◆第1次試験・基礎能力試験(多肢選択式) Ⅰ部(知能分野):2時間 Ⅱ部(知識分野):1時間30分 ◆第1次試験・総合論文試験:4時間 ◆第2次試験・政策課題討議試験:概ね2時間程度 ◆第2次試験・専門試験(記述式) Ⅰ部(小論文):2時間 Ⅱ部(口述式):1時間 ◆第2次試験・人物試験- |
| 合格基準・合格率 ・レベル等 |
[配点比率] 【院卒者試験】 ◆第1次試験・基礎能力試験(多肢選択式):2/15 ◆第1次試験・専門試験(多肢選択式):3/15 ◆第2次試験・専門試験(記述式):5/15 ◆第2次試験・政策課題討議試験(記述式):2/15 ◆第2次試験・人物試験:3/15 【院卒者試験[法務]】 ◆第1次試験・基礎能力試験(多肢選択式):2/7 ◆第2次試験・政策課題討議試験(記述式):2/7 ◆第2次試験・人物試験:3/7 【大卒程度試験】 ◆第1次試験・基礎能力試験(多肢選択式):2/15 ◆第1次試験・専門試験(多肢選択式):3/15 ◆第2次試験・専門試験(記述式):5/15 ◆第2次試験・政策論文試験:2/15 ◆第2次試験・人物試験:3/15 【大卒程度試験】 ◆第1次試験・基礎能力試験(多肢選択式):5/28 ◆第1次試験・総合論文試験:8/28 ◆第2次試験・政策課題討議試験:4/28 ◆第2次試験・専門試験(記述式):5/28 ◆第2次試験・人物試験:6/28 ※教養区分については、第1次試験の合格は基礎能力試験の結果によって決定し、総合論文試験は第1次試験合格者を対象として評定した上で、最終合格者の決定に反映 |
| 合格発表 | [最終合格発表] 【院卒者試験】 6月下旬 【院卒者試験[法務区分]】 10月中旬 【大卒程度試験】 6月下旬 【大卒程度試験[教養区分]】 12月中旬 |
| 受験料 | 無料 |
| 試験場所 | 人事院のHPにてご確認を |
| 実施団体等 | 人事院各地方事務局 |
| 管轄 | 人事院 |
![[国家公務員総合職] 情報/人気の国家資格取得](./img/header.jpg)

